人間関係がうまくいかず、「人とうまくいかないのは、こんな性格をしているからだ。自分の性格を変えたい」と、自分の性格について悩まれたことはないでしょうか。
どんな性格(=パーソナリティ)なら他者と良好な人間関係を築いていけるのか、またそのようなパーソナリティを形成するにはどうすればいいのかを、アドラー心理学の観点からお話しします。
スポンサーリンク
健康なパーソナリティとは?キーワードは「共同体感覚」
他者と良好な関係を築けるパーソナリティ(健康なパーソナリティ)の条件とは、何でしょうか?
キーワードは「共同体感覚」です。
共同体感覚について、『幸せになる勇気』では、こう解釈されています。
アドラーがドイツ語の「共同体感覚」を英語に翻訳する際に「social interest」という語を採用したことです。
これは「社会への関心」、もっと噛み砕いていえば、社会を形成する「他者」への関心、という意味になります。
(『幸せになる勇気』岸見一郎著 より引用)
「共同体感覚」とは、噛み砕いていえば「他者」への関心、他者の関心事に関心を寄せることなのですね。
たとえば、子供に勉強をさせるには、どうすればいいでしょうか?
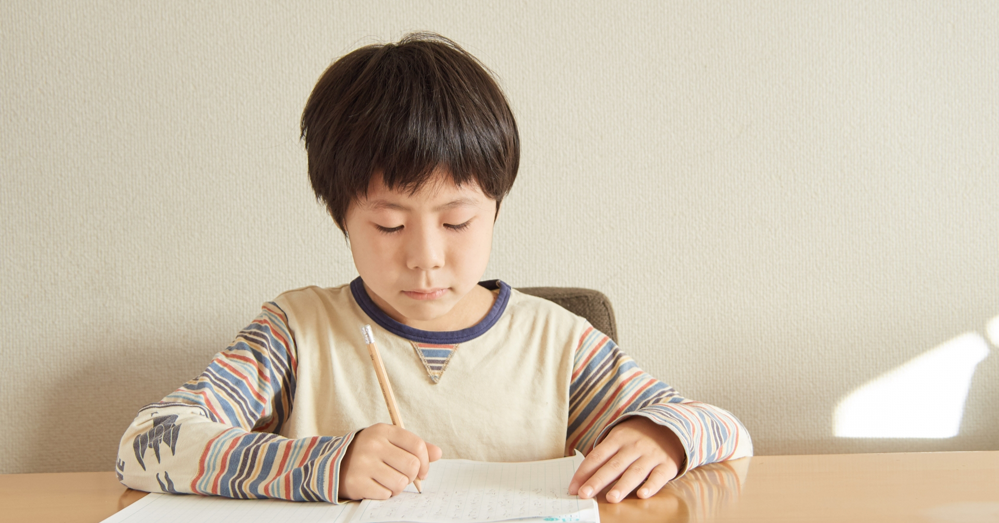
相手は何に関心があるかなどを無視して、単に「なぜ勉強しないのか。勉強しなさい」とだけ言えば、子供は心を閉ざし、ますます勉強という行為に向かわなくなってしまうでしょう。
勉強に向かわせる方法として、『幸せになる勇気』にはこう書かれています。
まったく勉強しようとしない生徒がいる。
ここで「なぜ勉強しないんだ」と問いただすのは、いっさいの尊敬を欠いた態度です。
そうではなく、まずは「もしも自分が彼と同じ心を持ち、同じ人生を持っていたら?」と考える。
(中略)
そうすれば「その自分」が、勉強という課題を前にどのような態度をとるか、なぜ勉強を拒絶するのか想像できるはずです。
(『幸せになる勇気』岸見一郎著 より引用)
相手の心に少しでも近づこうとし、勉強を拒絶する理由を知った上で、勉強についての誤解をしているなら、その思いを解きほぐしていく。
そして、勉強は建設的な行動であること、他者にも自分にもとても役立つことを伝えていく。そうすれば子供は勉強することへ前向きになっていくはずです。
これは勉強のみならず、仕事や頼み事をしてもらうときにも当てはまります。
相手ははどういう考えなのか?
なぜそういう考えに至ったのか?
どんなことに価値を感じているのか?
相手の信念は何か?
このようなことを知ってはじめて、相手の本当に望んでいること(あるいは誤解していること)がわかり、やってほしいことと相手のニーズを合わせること(あるいは誤解を解くこと)で、相手はその行動に積極的に踏み出していかれるでしょう。
相手にとっても、自らの関心事に関心を持ってもらえることは単純に嬉しいですよね。
存在を受け入れてもらえたと思えて、信頼感が高まるでしょう。
このことから、他者の関心事に関心を寄せることが、他者と良好な関係を築く第一の条件といえますね。
他者に関心を持たない人は、苦難の人生を歩まねならない
反対に、他者の関心事に関心を寄せることなく、相手から奉仕されることしか関心がない人がいたとしたら、その人は他者とどんな関係を築いていくでしょうか。

相手から見れば、そんな人とは一緒にいたくありませんね。
関係を築く以前に、相手はその人の前から去っていくでしょう。
では仮に、上司と部下のような上下関係がある場合はどうでしょうか。
その場合は、相手は逆らうことも去ることもできず、従わざるをえません。
しかしその関係は決して長続きしませんし、やがては仕返しを受けるでしょう。
暴言を吐かれたり、暴力を受けたりしたことを秘書が告発し、四方八方から批判を受けた国会議員がいたことは記憶に新しいですね。
相手から奉仕されることしか関心がない人は、他者を傷つけ、やがては自分もしっぺ返しを受ける、不健康なパーソナリティの人といえるでしょう。
アドラーの思想の影響を受けた1人に、『人を動かす』や『道は開ける』などのベストセラーで有名なデール・カーネギーがいます。
デール・カーネギーは、他者の関心事に関心を寄せることの大切さを、アドラーの言葉を引用して、こう語っています。
ウィーンの有名な心理学者アルフレッド・アドラーは、
その著書でこう言っている──
「他人のことに関心を持たない人は、苦難の人生を歩まねばならず、他人に対しても大きな迷惑をかける。
人間のあらゆる失敗はそういう人たちの間から生まれる」
心理学の書はたくさんあるが、どれを読んでもこれほど私たちにとって意味深い言葉には、めったに出くわさないだろう。
このアドラーの言葉は、何度も繰り返して味わう値打ちがある。
(『人を動かす』D・カーネギー著 より引用)
カーネギーがアドラーの言葉に大きな感銘を受けていたことがわかりますね。
「他人のことに関心を持たない人は、苦難の人生を歩まねばならず、他人に対しても大きな迷惑をかける」
胸に刻み、人と接するときにはぜひ教訓としていきたい言葉です。
相手は何を望んでいるのか、そのために自分にできることは何かを考え、貢献のための活動を行っていきたいですね。
まとめ
- 良好な関係を築く健康なパーソナリティの条件は「共同体感覚」、「共同体感覚」とは「他者の関心事に関心を寄せる」ことです
- 他者の関心事に関心を寄せ、相手のニーズを知ってこそ、適切な依頼ができるようになります。相手にとっても存在を受け入れてもらえることが嬉しく感じます
- 相手から奉仕されることしか考えない、他者に関心を持たない人は、相手との関係が長続きせず、仕返しをされ、苦難の人生を歩まねばならなくなるでしょう
引用した書籍
スポンサーリンク


