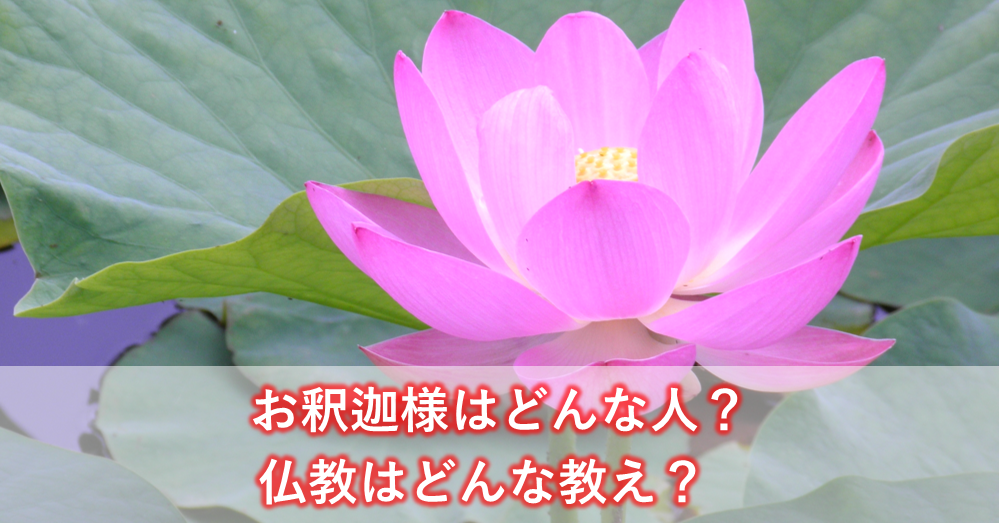仏教を説かれたお釈迦様は、悟りを開かれた後「人生は苦なり」と言われました。
お釈迦様が言われた通り、思い通りにならないことばかりで、悩み・問題がつきないのが人生ですね。
その苦しみばかりの人生、どうすれば幸せに生きていけるのでしょうか。
幸せに生きるための3ステップを紹介しています。
その3ステップは以下のものです。
- 「人生はドゥッカ」を認める
- 仏教のベース「因果応報」
- 六度万行(六波羅蜜)の実践
前回は1ステップ目の「『人生はドゥッカ』を認める」について書きました。
前回の記事はこちら
今回は2ステップ目、「仏教のベース『因果応報』」をご紹介します。
スポンサーリンク
誤解されている?「因果応報」の本当の意味
悩み・問題を解決するには、まず悩み・問題は「ある」ことを認め、それを受け入れることがその1ステップ目でした。
受け入れることで、次に、その悩み・問題の原因とは何かが考えられるようになります。
問題を誤魔化していては、原因を考えよういう気持ちにはなりませんね。
悩み・問題には原因があり、その原因を改善すれば問題は解決する。
その考えの元となっているのが「因果応報」です。
「因果応報」は元々、仏教の言葉です。日常でも使われているので、ほとんどの方が聞いたことあると思います。
どんなときに使われているでしょうか?
たとえば、
スピードの出し過ぎで警察に捕まってしまったときに、「それはあなたの因果応報ですよ」と言われたり、

消費期限のとっくに過ぎたものを食べたら、急な腹痛に見舞われたとき、「そんな消費期限の切れたものを食べるなんて。気の毒だけど因果応報だね」と言われたりするなどして使われています。

いずれも、悪い結果が返ってきたときに使われているのが共通していますね。
しかし本来の意味からすれば、悪い結果のみを指して因果応報というのは、実は誤りなのです。
因果応報は「原因に応じた結果が報いる」、「善い因には善い結果、悪い因には悪い結果が返ってくる」ということです。
だから悪い結果だけでなく、善い因に応じて善い結果が返ってきたときも「因果応報」なのです。
悪果を生み出す元とは?他人を恨むのは筋違い
ここで「因」というのは原因のことですが、仏教では特に私たちの「業(行い)」のことを指します。
「果」というのは「禍福」のことで、わかりやすくいうと私たちの「運命」のことです。
私たちの身に起こる運命は、私たちの行いによる、
よって、善い結果は善い行いによって生み出され、悪い結果は悪い行いによって引き起こる、
というのが因果応報なのです。
悪い結果が返ってくると、私たちは自分の行いによるものとはなかなか思えません。
上述の例でいえば、スピード違反で捕まったのは自分がスピードを出し過ぎていたからなのですが、その過ちを認めようとせず、「こんなところで見張っているなんて、ひどい」と警察を恨む気持ちが出てきます。
その他にも、仕事でのトラブルや人間関係のもつれの原因は私ではなく、誰か別の人のせい、悪いのはアイツだ、という気持ちになりがちです。
しかし因果応報からいえば、それらの悪果の根本の原因は私自身の行いによるのであり、他人を恨むのは筋違いといえるのです。
他人は因ではなく、あくまで「縁」と教えられます。
「縁」は間接的な原因であり、直接の原因ではありません(もちろん、悪い縁は更生さなければなりませんが)。
まず因に目を向ける、自分を変えることが大切ですね。
因に目を向けないまま他人を恨んでも、物事が良い方向に進むことはないでしょう。
ただ、因果応報とはいえ、すべてが自分の責任だと思い、過剰に抱え込む必要はありません。
あくまで悪果を招いたのは、自分の行動の一部分です。
その一部分を改め、善い行いに努めれば、トラブル・問題は解決に向かいますし、自己成長にもつながるでしょう。
このように仏教の基礎といわれる「因果応報」を受け入れ、まず自分自身の行いに目を向ける。
これが悩み・問題の解決の2ステップ目でした。
次回は最終ステップである「六度万行(六波羅蜜)の実践」について書いてきます。
まとめ
- 悩み・問題には原因があり、その原因を改善すれば問題は解決する。その元にあるのが「因果応報」の教えです。
因果応報は、原因に応じた結果が報いるということであり、善い行いによって善い結果が生み出され、悪い行いによって悪い結果が引き起こる、ということです - 悪果が返ってくると、私達はそれは自分によるものとは思えず、他人のせいにしたくなります。しかしその原因は私自身の行いによるのであり、他人を恨むのは筋違いなのです
- 問題を解決するには、因に目を向ける、自分を変えることがまず大切です。けれどすべてを過剰に抱え込む必要はありません
続きの記事はこちら
関連記事はこちら
スポンサーリンク